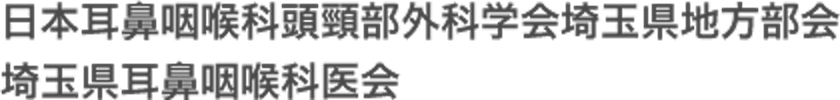-
 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会埼玉県地方部会
日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会埼玉県地方部会
会長 吉田 尚弘 -
ご挨拶
令和7年6月1日の埼玉県地方部会総会において、前地方部会長の菅澤正先生より引き継ぎ、地方部会長を担当することになりましたのでご挨拶申し上げます。
以前、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会125周年記念誌に歴代の資料を参考に埼玉県地方部会の歴史を記載させていただいたことがあります。埼玉県は医育機関の設立が比較的遅かった点や複数の大学附属病院が存在することから地方部会の組織および運営形態は他の都道府県とはやや異なっておりました。埼玉県地方部会と同時に埼玉県耳鼻咽喉科医会の会員となり、日本耳鼻咽喉科学会の活動と関連した学術的な活動を行っていると同時に医会としての地域医療に対する活動を行うこととなりました。
埼玉県地方部会発足後、耳鼻咽喉科医会と表裏一体となって運営する基本的方針をとっていた埼玉県地方部会では、学術的活動とともに地域医療、救急医療の整備に対する県、会員、医療機関、医師会との連携を図る活動も多くおこなってきました。東西の距離が長くかつ面積も広く、東西間の交通網が十分ではない埼玉県の地理的特徴から、埼玉県地方部会における活動には、地域をブロックに分けて各地域での地域医療に対する取り組みの必要性も検討されその時々に柔軟に対応されてきました。
平成29年より従来の埼玉県耳鼻咽喉科医会と埼玉県地方部会の組織を分けて会則を変更し、地方部会では、さらに学術的な側面を中心に進めていくことになっています。診療所はもとより医育機関その関連病院、地域中核病院が相互に協力しながら埼玉県の耳鼻咽喉科頭頸部外科医療を発展させていく必要があります。また、埼玉県地方部会は埼玉県耳鼻咽喉科医会と連携をとりながら、中心となる領域を各々が認識しながら、開業医、中核病院・医育機関の勤務医が一体となって埼玉県の耳鼻咽喉科医療の充実を引き続き図っていくことが求められています。
- 高齢化社会に対応した医療の提供
- 軽度中等度難聴者に対する補聴器購入費補助制度の拡大と早期の補聴器装用の啓発
耳鼻咽喉科医と認定補聴器技能者の連携を中心とした補聴ネットワークの構築 - 嚥下障害に対する診断、治療、在宅療養を要する患者に対する外科治療などのネットワークの構築
- 軽度中等度難聴者に対する補聴器購入費補助制度の拡大と早期の補聴器装用の啓発
- 産婦人科・小児科と連携した新生児聴覚スクリーニングとサイトメガロウイルス検査、小児難聴への療育拡充
- 花粉症ゼロ対策に対応した地域ネットワークの構築
- 咽頭がん: HPV感染に対するワクチンの啓発と取り組み
- 学校保健: 指導、動向調査を行い、学校保健の向上を目指し耳鼻咽喉科学校健診を継続
- 救急医療・災害医療: 近い将来直下型地震などの災害発生の可能性は高まっています。救急医療と災害医療は地域で対応する必要がある点で共通性があり、災害に対しての地域としての対応スキームを考える時期に来ています。各地区、各立場から一次医療を担当される診療所の先生にも中心になっていただき方策を検討する必要があると考えています。
- 労働衛生: 騒音性難聴 音響性聴覚障害 イヤホン、ヘッドホン難聴に対する啓発と対応
- 診療につながる専門的知識の向上を目的とした学術集会、さらにはweb臨床セミナーによる情報発信
日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会の各委員会で中心的な役割を果たされている会員も多くおられます。情報・連携を密にとり、経験のある先生方の大所高所からのご意見とともに現在埼玉県の医療を中心的に支えてくださっている先生そして若手の先生の意見も積極的に幅広く取り入れられる体制で運営してまいりたいと考えています。
埼玉県は、令和7年には人口737万人となり、今後人口は減少には転ずるものの減少は緩やかで2030年にはなお720万人以上の人口が見込まれ、高齢者の人口の増加が予測される全国的にも特徴のある県の一つです。会員の先生一人一人のご協力をいただき、埼玉県の耳鼻咽喉科頭頸部外科医療をさらに充実したものとするように努力してまいりたいと思います。ご支援、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 - 高齢化社会に対応した医療の提供
-

埼玉県耳鼻咽喉科医会
会長 登坂 薫 -
ご挨拶
1.医会の成り立ちと活動について
埼玉県では、長年にわたり地方部会と医会が一体となって活動してきました。しかし、日耳鼻本部の方針により医会の独立が進められ、当県も議論を重ねた末、最終的に分離の方針を受け入れる形となりました。
数年前、日耳鼻から日本臨床耳鼻咽喉科医会が独立した際、埼玉県でも組織・会計を分け、「埼玉県耳鼻咽喉科医会」として新たに発足しました。会費は徴収せず、地方部会からの委託金で運営し、毎年2月に学術講演会を開催しています。講演内容は、恒例の「保険診療」「医事問題」に加え、今年度は「学校保健」「補聴器キーパーソン会議」、さらに特別項目として「耳鼻咽喉科救急医療体制」を新たに設けました。また特別講演では、地方部会の組織改編を機に災害対策委員会が新設されたことを受け、「埼玉県の災害医療の現状」と題して、さいたま赤十字病院 田口茂正先生(高度救命救急センター長)をお招きする予定です。
これまで埼玉県では、耳鼻科開業医が地方部会長を務める伝統があり、浦和の宮﨑和先生や川越の片岡紀男先生(現顧問)など、大学教授と交互に就任し地域医療を支えてこられました。開業医としての診療に加え、部会長という重責を担われたご尽力に、改めて深く敬意を表します。
しかし近年は、開業医の先生方に役員就任をお願いしてもお引き受けいただくのが難しく、人選に苦慮しているのが実情です。現在は13名の開業医の先生方に理事・監事としてご参加いただいており、大変ありがたく思っております。
地方部会の業務は、医会と完全に分離しているわけではありません。総務、会計、広報、学術、保険医療、学校保健、医療安全・産業保健、救急医療・災害医療、補聴器キーパーソンなど、あらゆる分野で開業医と勤務医が連携して活動しています。
他県では分離しているところもありますが、多くの地方部会は一体的に運営されています。埼玉県でも、今後も一体となった活動を継続していけるよう、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
2.埼玉県特殊救急医療体制(耳鼻咽喉科)整備事業について
(1)経緯
埼玉県医師会役員会で毎月報告される「#7119事業」の中で、「案内できない診療科」第一位が常に耳鼻咽喉科でした。県もこの状況を重く受け止め、医師会および地方部会と協議を重ねた結果、平成26年秋、総額1700万円の予算による「埼玉県特殊救急医療体制(耳鼻咽喉科)整備事業」がスタートしました。
(2)事業内容
日曜・祝日・年末年始の午前9時~午後5時に、県を東西に分けて輪番制で実施しました。重症例に対応するため、大学病院などの二次輪番体制も併設しています。
患者数は年々増加していましたが、コロナ禍で一時半減し、現在はほぼ回復しています。1日あたり患者数は0~200人超と大きな幅があります。二次紹介は月平均2件弱です。
現在、10郡市医師会が休日耳鼻科救急を実施しており、県当番と連携した体制を構築しています。ただし、県と市町村双方からの報酬支払いができない制度上の制約があり、関係各位にはご理解をお願いしています。
(3)検討・課題
本事業を行いながら、医師会、地方部会、医療整備課で何回も委員会を開き、次のような課題が議論されてきました。- 参加医療機関の減少(特に西地区)
- 若手医師・新規開業医の参加不足
- 特定医療機関への負担集中
- 東西統一の是非
- 報酬見直しの必要性
- 当番義務化の検討
- 二次医療機関との連携強化(専用回線・携帯貸与など)
(4)埼玉県医師会での訴え
県医師会理事会や郡市医師会長会議において、「当番の担い手不足」「若手不参加」「参加医師の高齢化」「同一医療機関への負担集中」といった現状を繰り返し訴えてきました。
(5)埼玉県への要望書提出
毎年同じ議論が続き、県側の人事異動により話が進展しないため、令和7年3月12日、金井埼玉県医師会長名で大野県知事宛に正式な要望書を提出しました。内容は以下の通りです。
- 県事業として耳鼻科救急専用施設を新設し、当番医師がそこへ出向く体制の構築
- 東西を統一した一次医療体制への移行(令和8年度から)
- 参加医療機関への補助金増額
- 二次当番医師と直接連絡できるよう、専用携帯電話の貸与
(6)お願い
耳鼻咽喉科救急体制は、県民の安心と安全を守るために欠かせない仕組みです。現場の先生方のご協力なしには成り立ちません。この現状をご理解の上、ぜひ当番制度へのご参加をお願いいたします。皆さまの力が、この体制を支える大きな原動力となります。